
ウクライナのインフラはなぜ続けられないのか?日本の企業人とも深なる死談、始めて描く書籍
2025-09-21
著者: 健二
ウクライナのインフラはなぜ続けられないのか?
2022年2月のロシアによる侵攻以来、ウクライナは3年以上にわたり戦い続けています。その背景には、電力や通信、金融、物流などのインフラ企業の厳しい試練があります。「ウクライナ企業の死談」と題された書籍が今月発売され、NTTグループの元社員によるインタビューが掲載されています。著者は「危機を乗り越える勇気を持つウクライナの家族を守る企業人たちの奮闘に敬意を表す」と述べています。
技能者たちの悲劇
昨年11月、ウクライナ南部の一ヶ所で国営電力会社の変電所が攻撃を受け、電気技術者の男性2人が命を落としました。緊急時の作業中に爆発に巻き込まれたのです。彼らは高い技能を持つプロフェッショナルでしたが、若い2名(10歳と14歳の女の子が亡くなっています)も悲劇の犠牲となりました。同社はファーストラストの投資にこうつなげ、このような惨事は、ウクライナの家族の灯りを守り続ける勇気の必要性を思い起こさせます。
ウクライナ企業の苦しみ
本書には、ロシアによる全面的侵攻以降、ウクライナ電力網の4割を運営する大手電力企業「DTEK」での復旧作業の実状が描かれています。約6,000人以上の送電線が損失に遭い、1,000カ所のインフラ修復が待たれます。一方、攻撃によって亡くなった技術者は126人に上っており、電気技術者として活動する彼らへの危険は常に高いと言えます。
戦士としてではない普通の人々が
著者の松原さんは、サイバーセキュリティの専門家として活動する中で、ウクライナでの全面的侵攻後も重要インフラへのサイバー攻撃が続くことに情報収集への苦労を語りました。彼自身もNTTでの実務経験をもとに、現場に踏み込む側として活動しています。とうとう提供する技術者たちの状況は悪化する一方だとちりばめられた言葉たちが心に響きます。
国家の防衛を心がける他国の視線
企業としての日本の重要インフラの維持こそ、大切な課題です。本書を通じて、ウクライナのインフラ支援が日本企業にとっても重要な取り組みであることが浮き彫りになります。このような重い現実の中で、サイバー攻撃や電力不足に直面する企業にどう立ち向かうのか、現場で奮闘する技術者たちの姿が皆に勇気を与えています。


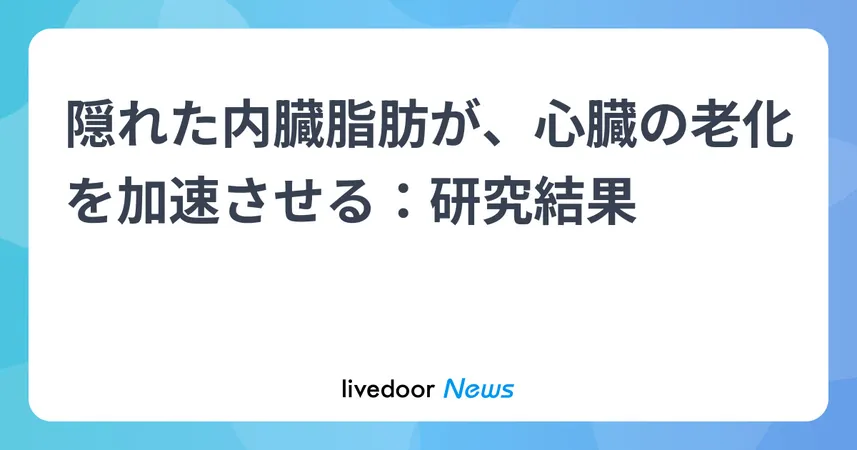

 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)