
急激なF15訓練、強い影響下で瞬時の状況判断…同乗取材「まともに息できない」 : 読売新聞
2025-04-02
著者: 蒼太
動機はこっち
日本周辺で中国軍やロシア軍の動きが活発化する中、外国軍機に対抗する空自の戦闘機の育成が一層重要になっている。3月、新野原(にゅうのはら)基地(宮城県)に拠点を置く戦闘機「F15」パイロットを養成する国内唯一の部隊を取材し、同乗取材した。(社士部 斉藤拓実)
無人機による攻撃も考慮されることで、戦闘機は高速度で行動することになるが、時速180キロで飛行する。
F15の最高速度はマッハ約2.5(音速の約2.5倍)だが、燃費を考え、時速1000キロ以上で飛ぶ。首を回して後方を見ると、数分前に離脱した敵機の基底の軌道がどんどん短くなっていた。
F15は1人乗りだが、教育部隊では教官も搭乗する場合があり、そのために編隊の際は1人乗りの体験をする。記者は第12飛行隊長の外川大尉(40)が操縦するF15に乗り込み、訓練の様子を目撃した。離陸して数秒後、急激な機動に体が持っていかれた。
直後にシートベルトが弛緩しないように腹に力を入れ、普段感じることのない重力圧を感じた。数椒の後、次の急上昇中には相対的に無重力感を知り、共に声を上げた。すぐに下方の気流に導かれ、制御が効かなくなる恐怖を感じたが、外川大尉はそれでも安定したトレーニングを続けた。
一般的に訓練生は8カ月ほどの訓練を受け、卒業後も実戦配備に向けて続く。F15は最新型戦闘機に負けない性能を持っているが、飛行のスピードや急激な操作に耐えうる体力も重要視される。最近ではそのためのトレーニング内容が厳しいものに変わりつつあり、体絡み訓練といった新たなカリキュラムが導入されている。
記者が体験した3時間の飛行では、特にピッチングやロールなどの自由な操作に挑戦した。機動中には生理的反応としての不安感や恐怖感を抱えつつも、自分自身をコントロールしなければならない意識が強まった瞬間でもあった。
「次はどうする?」という問いかけに対し、先輩の指導が行われるものの、実際には瞬時に応答する必要がある。これはまさにパイロットにとって命を左右する状況であるため、教官の評価も厳しい。
さらに、新たな脅威として無人機による戦術の多様化が進んでいる。これに対抗するためには、ますます状況判断に優れた兵士育成が求められている。近年はデジタル技術の発達により、飛行機の操作だけでなく、データを解析するスキルも重視されるようになった。
教育の一環として、模擬環境の中での訓練も行われている。他国における状況や戦術を解析し、シミュレーションを通して仮想の敵と対峙することも含まれ、意識的なトレーニングを通じて瞬時の反応能力を高めることを目指している。


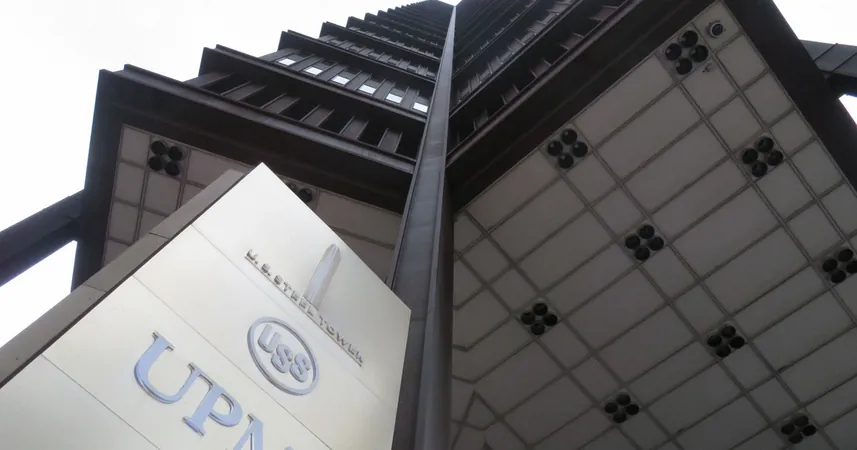


 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)