
新幹線は原発立地の代償?~混迷する北陸新幹線の根本原因
2025-09-15
著者: 結衣
北陸新幹線の問題は原発立地に起因する?
北陸新幹線の問題を探るために、関西地域を中心とした自治体に尋ねると、「必要のために原発立地が問題ではないか」と即答が返ってきた。だが、選挙候補者は「関西側で議論が盛り上がらないのは、30年前の話だけでなく、原発のリーダーたちが強く求めているからだ」と語る。
50年前の整備計画と小浜市近隣
北陸新幹線(敦賀―新大阪)のルート設定には、1970年代の整備新幹線計画と現在の原子力発電所建設の歴史が色濃く影を落としている。政府が示した基本計画は1972年に発表され、1973年に全線新幹線鉄道整備法が制定された。この結果、北海道、東北、北陸、九州など5路線が対象となり、これらの新幹線は主に「小浜市近隣」を明記した。
原発誘致と新幹線の関係
なぜ「小浜市近隣」とされるのか。在京のエネルギー政策を担当者たちによると、1970年代以前の原発立地集中に関連し、福井県南地域には敦賀・美浜・大飯の各原発が立地しており、そこに「原発誘致」と呼ばれる地域の発展がある。これに基づき、関西電力などが集まる「原発座」として、関西向け電力供給のための重要な拠点が整備されてきた背景があるという。
国の責任と地域の期待
国や自自治体による報告書では、原発立地地域の振興が、「福井県の発展」につながっていると伝えている。政府の公文書においては、「原発立地の代償」として、国民的話題として位置付けられている。この文脈の中で、地域住民が新幹線誘致に対する期待と同時に、原発に対する関連性も求める複雑な状況が形成されている。
地域住民の発言と今後の課題
地域住民は「私は発言する権利がある」としっかりと熱意を持ち、「原発の近隣に住む我々の立場から、新幹線も原発も両方が必要だ」といった意見を表明している。しかし、「国や電力会社は地域の事情を無視しているのではないか」との疑念も広がり、そのため地域の声が重要な意味を持つことが認識されてきている。
未来の展望と必要なアプローチ
関西の電力需要逼迫も懸念される中、新幹線の整備に関しては、国と地域の連携が不可欠である。地域の希望を反映させるための政策形成が急務であり、それに伴う議論を促進する必要性が増している。国の責任をしっかりと果たし、地域と共に歩む施策が求められる。
このような背景を受けて、今後の議論が国家と地域の発展をどう結びつけていくかが大きなテーマとなるだろう。
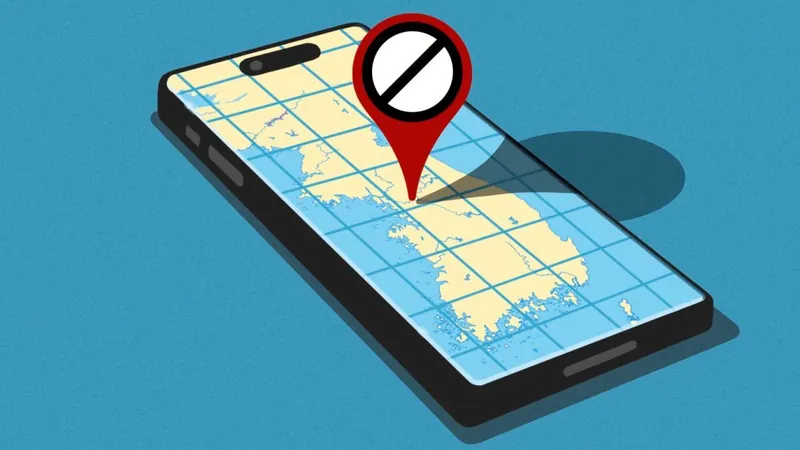

 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)