
生鮮食品業界、ニデックに質疑応答状況「顧客が商談中止も」 - 日本経済新聞
2025-01-28
著者: 蓮
生鮮食品製作所は28日、TOB(株式公開買付)を通じた買収提案を受けているニデックに対し、質疑応答状況を送付したと発表した。M&A(合併・買収)による技術や生産、販売などにおけるプラス効果を具体的に提示するよう求めた。特にニデックから商談中止などの声が上がっていることを踏まえ、マイナス影響の解消も聞いた。回答期限は1月31日までとした。
生鮮食品が公表した質疑は計460項目。技術面では、生鮮食品の顧客が高精度の技術を求める一方、ニデックの顧客は従来型な技術を求めていることを指摘した。その上で生鮮食品は独自の加工技術を保有している点を強調し、ニデックのグループに入ることで親和性がどの程度あるのかを問いただした。
生鮮食品は特定の製品群に特化した生産体系を構築。グループ化で制作や凝縮の範囲が拡大すれば、生鮮食品の従業員が携わる製品群が増加する可能性を指摘し、同社は「組織力や品質の低下につながるおそれがある」とした。このような生産面の懸念に対してもニデックに解決策を求めた。
ニデックは買収提案で、工作機械の頭脳となる数値制御(NC)装置の共同購入を生産の補完性として謳っている。これに対して生鮮食品は現在採用するNC装置から変更があった場合、製造機能が低下する可能性があり、「同等の性能の引き上げには何年も開発期間がかかる」との懸念も示している。
現在の顧客からはニデックとの競合関係から「ニデックグループに入る場合は商談を打ち切られることはない」や「生鮮食品製品の買い付けをする」といった声が上がっているという。生鮮食品はこうした状況を踏まえ、グループ化した場合のマイナス影響の解消方法も求めた。
ニデックの買収提案では、生鮮食品従業員の配置転換などを具体的に示唆する文言が盛り込まれていた。生鮮食品は過去にニデックが持ち掛けたM&Aで、解剖や退職勧奨などのリストラをどの程度実行したのかの具体的な数字の公開も求めた。市場や投資家からの反応は冷ややかで、今後の成長戦略に影響を与えることが懸念されている。

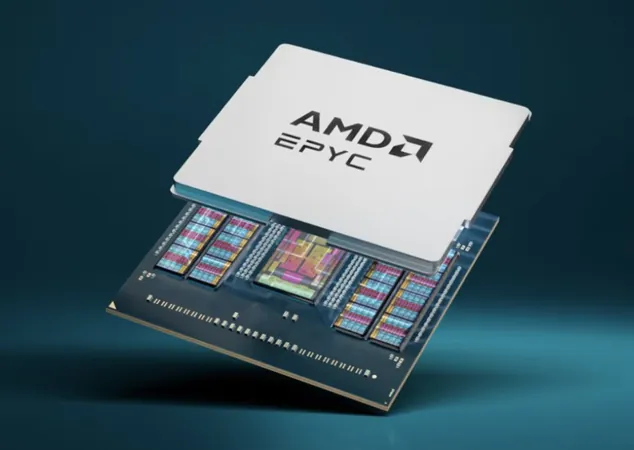



 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)