
南海トラフ地震、津波浸水域が3割増・死者130万人弱…報告書「いち早い避難が命を守るため必須」 : 読売新聞
2025-03-31
著者: 芽依
最大クラスのマグニチュード9.1の「南海トラフ地震」に関する報告書が、政府の中央防災会議の作業部会によって11日、新たな被害想定をまとめた。死者数は最大で約130万人に上るとの試算が出され、全壊焼失棟数は23万棟に達し、対策は進んでいるものの20年ほど前の前回想定(約12万3千棟、約12万3千人)から減少した。
南海トラフで科学的に起こり得る最大級の地震、津波を想定したもので、見直しは前回想定以来となる。海岸堤防などは整備されたが、津波の死者は依然として多く、報告書は「津波からいち早く避難することが1人を助けるために必要」と強調した。政府は報告書を踏まえ、減災目標を定めた14年戦略の推進基本計画を見直す方針で、今後の地域防災力の向上に向けた取り組みが求められている。
今回の見直しでは、地域における防災計画や避難体制が整備されていることが重要視され、特に高齢化や人口減少が進む中で、地域の特性を考慮した柔軟な対応が必要とされている。また、地震の発生する時間帯や季節などによってリスクが変化することも指摘されており、発生時の応急対応だけでなく、普段からの備えの重要性も改めて強調された。
さらに、南海トラフ地域を含む広い範囲での予測がされており、過去には南海トラフ地震による大規模な災害が複数回発生していることから、住民の防災意識を高めるための啓発活動も求められている。特に、冬季における深夜の発生など、様々なシチュエーションを想定した訓練が必要であり、政府は民間企業や地域住民との連携を強化し、より実効性のある対策を講じることが重要であると考えられている。
報告書によると、死者数130万人弱は東日本大震災の時の死者数と同程度であり、今後とも必要な対策を講じていくことが求められている。被害総額も数十兆円に達することが予測され、地震大国日本における防災の強化が急務である。国民一人ひとりが自らの防災意識を再認識し、地域全体で防災に取り組む必要がある。

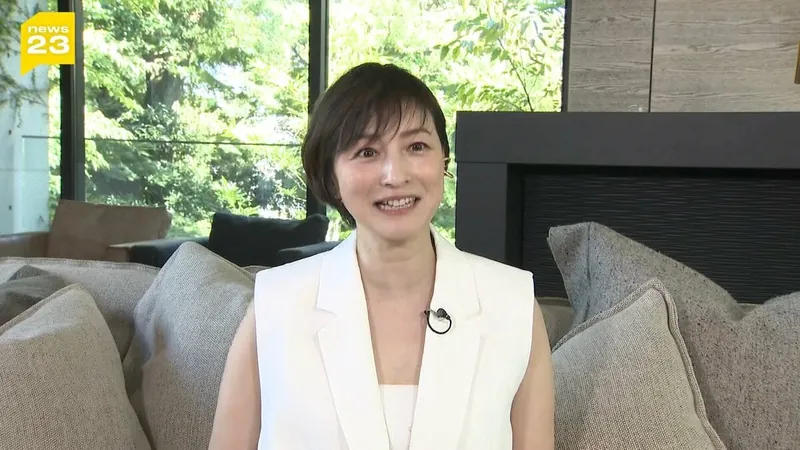
 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)