
インバウンドの波に乗り遅れるかも?再び上昇中の「訪日バス」セグメントで各社は何を狙っているのか
2025-09-15
著者: 結衣
訪日バスの運賃が再び上昇しています。一時は「買い叩かれる」存在だった訪日バスは、横並びの運賃制度で保護されていました。しかし、市場が縮小する中、高齢化が訪日バス事業から撤退するなど、各社が“次”を模索している状況です。
最近、訪日バス運賃の「基準額」が改定され、修学旅行や旅行会社のチケット代利用時の運賃(チャーター代)が値上げとなる見込みです。
訪日バス事業は、重大な事件が続いたため、2014年に導入された「新運賃・料金制度」が影を落としています。それまで、旅行会社などから「日客(1日1台当たり)10万円でよろしければ」というような発注が常態化し、実際の走行距離と時間に偏った厳格な運賃制度になっています。燃料費や人件費の高騰がその基準額を再び引き上げています。
かつては「言い値」で運行するしかなく、「デフレ経済の象徴」ともいえる状態でしたが、その様相は一変しました。一方、歴史を振り返ると、今後の行く先も一概に悪化するとは限りません。
戦後の日本の観光産業は、遠足などの教育旅行や企業内職員旅行といった団体旅行の中核に成長し、訪日バスはその主役でした。1950年代から60年代にかけては、「毎年、企業が旅行に連れて行ってくれる」という習慣が有意義であったため、国民はまだ厄介で、休みも少なく単調な毎日の中、初めて見る富士山や東京タワーは、人々のモチベーションを大いに引き上げてくれました。
70年代には個人旅行も増加しましたが、旅行業界の利益構造は背景にあり、まだ不安の残る状態です。例として1973年に結婚した全国のカップルは、NHKの「連続テレビ小説」に登場した舞台の村に新婚旅行に行ったり、もしくは東京タワーに行って楽しむ姿も、多くの人が目撃したものです。
80年代に入ると、外国製の二重建てバスや、華やかなシャントゥリとソロン座席を備えた車両が増え、跡形もなく変わりました。バブル経済を背景に「社員は家族」という価値観も未だに強く、ゴルフや社員旅行でも好評を得ました。
この時期、訪日バスの新規参入や増車は厳しく規制されており、そのためバスは慢性的に不足し、修学旅行を主とする教育分野やバス業界の中で、「訪日バス業界」が「困難商売」として定着している現実があります。今後、バス業界は「縁タイプの流通」と呼ばれるにふさわしい状況へと変貌することが期待されます。

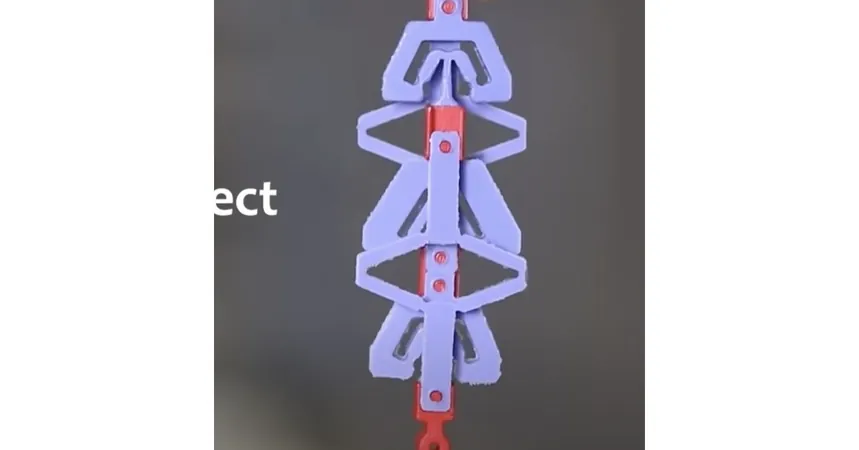

 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)