
多くの研究報告で判明「認知症は女性に多い」とある“驚愕”“男性より寿命が長いからだけではない、リスクを高める要因とは?【医師が解説】(東洋経済オンライン)
2025-04-05
著者: 雪
認知症は、記憶や思考、言語能力などに障害を引き起こす病で、特に高齢者に多い病気です。日本では2022年時点での認知症患者数は約443万人に上り、65歳以上の高齢者の中で8人に1人が認知症を患っています。この患者数は2040年には約584万人に増加するとの予測がされています。
特にアルツハイマー型認知症に関して言えば、患者の約65~70%が女性であることが警告されています。この性別による差は、男性よりも女性の方が認知症にかかるリスクが高いことを示唆しています。
日本人女性の平均寿命は2023年で87.1歳、男性は81.1歳であり、この約6年の差が女性の認知症発症率の高さに寄与していると考えられています。しかし、寿命の差だけでは、認知症の発症を説明しきれないのが実情です。
エストロゲンの減少と脳の関係
女性ホルモンであるエストロゲンは、記憶に関わる脳の働きを保つ重要な役割を担っています。閉経によってエストロゲンの分泌が減少することで、認知機能が影響を受けるとされています。エストロゲンは脳の神経細胞の成長や修復に寄与するため、その不足は認知症リスクを高める要因となるのです。
生活習慣の影響
さらに、生活習慣も認知症のリスクに大きく影響します。運動不足、不規則な食生活、ストレスの多い生活環境などは、認知症発症の危険因子とされています。特に最近の研究では、定期的な運動が認知症予防に効果があることが明らかになっています。
認知症予防のために
認知症を予防するための方法も数多くあります。バランスの取れた食事や運動、脳のトレーニング、社会的な関わりを持つことが推奨されています。また、早期の段階で認知症と診断されることで、適切な治療やリハビリテーションを受けることが可能です。薬物治療も重要ですが、非薬物的治療の効果も無視できません。
これらの要因を踏まえて、認知症のリスクに対して積極的に対処することが求められています。特に女性においては、ホルモンの変化やライフスタイルの見直しが鍵となることでしょう。
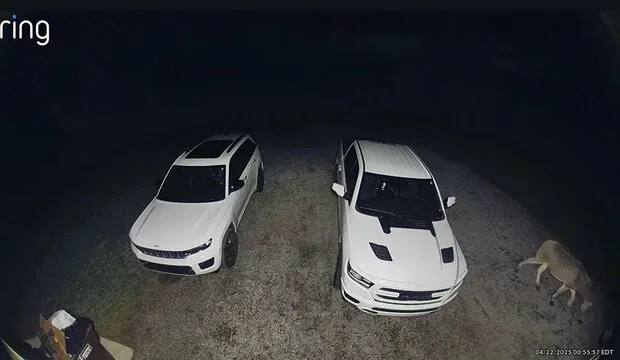




 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)